子どもの手当・医療費助成
新着情報
-
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、「児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ」...(2024年11月12日 子育て支援課)
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、「児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」が行われます。
【関連リンク】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(264KB)
令和3年3月分から児童扶養手当制度が変更されます
障害基礎年金等を受給されているひとり親の方も受給可能となる場合があります。
【関連リンク】 児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している母(父)又は母(父)に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
母、父又は養育者が監護している場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺棄等で父母がいるかいないか明らかでない児童
※以下の場合等であれば手当は受給できません。
- 母(父)、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
児童扶養手当の手続き
市役所(22番窓口)手続きをしてください。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止等のため、緊急事態措置期間における郵送による受付も行っております。
認定請求等の手続きに際し、事前にお電話で内容を確認させていただいたうえで、請求書類等を郵送させていただきますので、子育て支援課家庭係(072-972-1563(直通))までお問い合わせください。
○必要な書類について
- 児童扶養手当認定請求書(子育て支援課の窓口にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本 <注>
- 銀行預金通帳(請求者本人名義のもの)、キャッシュカード等
- 健康保険証(親・子全員分)
- マイナンバーカード又は通知カード
- その他必要な書類(ケースにより異なりますので係におたずねください)
<注意>離婚直後で新しい戸籍ができていない場合や、本籍地が遠方で戸籍の入手に時間がかかる場合などについて、柏原市では、離婚届受理証明書による仮受付が可能です。詳しくはお問い合わせください。
○所得制限について(令和6年11月以降)
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。
下記の表による額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
母(父)又は養育者 配偶者、扶養義務者等 扶養親族
等の数全部支給の
所得制限限度額一部支給の
所得制限限度額所得制限限度額 0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満 1人 107万円未満
246万円未満 274万円未満 2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満 3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満 4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満 5人 259万円未満 398万円未満 426万円未満 以下1人増すごとに
38万円加算以下1人増すごとに
38万円加算以下1人増すごとに
38万円加算備考 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、19~22歳の特定扶養親族及び16~18歳の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等が全て70歳以上の場合は1人を除く) 養育費について
この制度においては、母(養育者は除く)または児童が児童の父から養育費(その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等)を受け取っている場合、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が母の所得に算入されます。
養育費と認定される詳しい範囲などについては係におたずねください。手当の月額について
令和6年4月からの手当額(月額)は、次のとおりです。
区分 全部支給 一部支給 第1子 45,500円 45,490円~10,740円
(所得に応じて10円きざみの額)
第2子以降 10,750円
10,740円~5,380円
(所得に応じて10円きざみの額)
※一部支給額の計算方法
・第1子 手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.025}
・第2子以降 手当月額=10,740円-{(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0038561}
※物価スライドにより改定される場合があります。
公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、差額分の手当を受給できます!
これまで公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、ほか)が児童扶養手当の額よりも高いため、申請していなかった方の中にも平成28年8月からの第2子加算、第3子以降の加算額が増額されたことにより、その差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。
新たに児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。年金の証書など(基礎年金番号と年金額がわかるもの)をご用意のうえ、子育て支援課家庭係までお問い合わせください。
<注意>認定日は、申請のあった月の翌月からとなります。
手当の支払期月
手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支払は、年6回(奇数月:1月、3月、5月、7月、9月、11月)それぞれの支払月の前月分までの2ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込されます。※児童扶養手当を継続して受けるために
毎年8月に、市役所にて現況届(継続)の手続きをしていただく必要があります。
手続きをしていただくことによって、引き続き児童扶養手当を受けられる資格があるかどうかを審査いたします。現況届を行わないと11月分以降の児童扶養手当を継続して受けることができません。また期限を過ぎて現況届をの手続きを行った場合は、児童扶養手当の支給が遅れる場合があります。なお、現在所得制限により児童扶養手当の支給が停止になっている人も、現況届の手続きは行ってください。
現況届について、受付の日程や手続き等に必要な書類に関しましては係までお問い合わせください。 ※毎年8月までに現況届の案内の通知文を送付いたします。<ご注意ください!>
◎現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法22条の規定により手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
次のようなときは必ず届け出をしてください
○児童扶養手当を受ける資格がなくなったとき → 資格喪失届
<児童扶養手当を受ける資格がなくなる主な例>
(1) ・婚姻したとき
・婚姻届は提出していないが、男性(女性)と同居し社会通念上夫婦として認められるような関係になったとき
・ 男性(女性)と同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があったり、生活費の補助を受けていたりするとき
・ 住民票上(世帯分離も含む)、男性(女性)と同居が確認された場合
(2) 受給者が児童を養育しなくなったとき
(3) 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く) に入所したとき
(4) 受給者が遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったとき
※年金の月額支給額によっては引き続き児童扶養手当の受給が可能な場合もありますので家庭係までお問い合わせください。 (5) その他、児童扶養手当を受けることができる人の条件にあてはまらなくなったとき○受給者(母・父・養育者)または児童の氏名が変わったとき → 氏名変更届
○手当の支給先金融機関を変更したいとき → 金融機関変更届
○住所が変わったとき → 住所変更届
市内転居について、新しいお住まいが賃貸住宅の場合、賃貸契約書の写しの提出が必要です。 他の市町村へ転出される場合には、住所変更の手続きを行ってから、転出先の市町村の児童扶養手当担当課でも手続きをしてください。また、新たに扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹など)と同居または別居される場合も届出が必要です。扶養義務者の所得によっては、今まで受けられていた手当が支給停止になる場合や、反対に今まで支給停止されていた手当が受けられるようになる場合があります。○養育している児童の人数が増減するとき → 額改定請求書/額改定届
-
柏原市ではお子様の健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。 対象者は、定められた範囲において医療費の助成を受けることができます。 所得制限はご...(2023年8月24日 子育て支援課)
柏原市ではお子様の健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。
対象者は、定められた範囲において医療費の助成を受けることができます。
所得制限はございません。内容は以下のとおりです。また、令和2年10月からの助成対象の拡大については 助成拡大についてはこちらをご覧ください。
●助成対象者
助成対象 未就学児童 小学生 中学生 高校生等 入院(食事代含む) 〇 〇 〇 (〇)※ 通院(調剤含む) 〇 〇 〇 (〇)※ ※令和2年10月1日から対象年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大しました。
ただし、次に該当する方は対象外となります。
1.生活保護を受給中の方
2.児童福祉法に基づく措置による医療費の支給を受けている方
3.障害者医療福祉助成制度による医療費の支給を受けている方
4.ひとり親家庭医療費助成制度による医療費の支給を受けている方●医療証の申請
※令和2年10月1日からの年齢拡大に伴う医療証の申請手続きについては、上記を「助成拡大についてはこちら」をご参照ください。
※出生や転入等の方が助成を受けるためには『こども医療証』が必要です。
下記のものをご持参のうえ、申請してください。医療証を発行いたします。
【申請に必要なもの】
・申請書(ダウンロード)
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)
○健康保険証の内容が変更になった方
【申請に必要なもの】
・受給資格事項変更・喪失届(ダウンロード)
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)●助成の範囲
医療費(保険適用分)の自己負担分から一部自己負担金を除いた額。
【一部自己負担金について】
・一日あたり一人一医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です。
(同一月内2回まで。同一の医療機関であれば3回目以降は無料)。
・同一の医療機関でも入院と外来、歯科と歯科以外は別扱いとなりますので、
それぞれに自己負担が必要です。
・処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)、
薬局でのご負担はありません。
・1ヶ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた
差額については、払い戻しの申請ができます。●助成方法
<大阪府内の医療機関で受診する場合>
医療機関等で健康保険証とこども医療証を提示してください。
<大阪府外の医療機関で受診する場合>
いったん医療費(食事代)をお支払いいただき、領収証を持参のうえ、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は、手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。
●払戻の申請方法
下記のものをご持参の上、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。
【申請に必要なもの】
・支給申請書(ダウンロード)※子育て支援課窓口にもございます。
・健康保険証
・こども医療証
・領収書(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)※払戻の申請は郵送でも受け付けております。ダウンロードした支給申請書に必要事項を記入後、領収書とともに子育て支援課家庭係までお送りください。
【高額療養費に該当する場合や、治療用の装具・眼鏡等の申請をする場合】
こども医療費助成の申請をするまでに、先にご加入の健康保険へ高額療養費の申請してください。
領収書(コピー)に加えて、健康保険から発行されます支給決定通知書を添えてこども医療費助成の申請をしてください。
また、治療用の装具・眼鏡の申請には、上記の【申請に必要なもの】の他、支給決定通知書、
医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)及び領収書のコピーの添付も必要です。※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをおとりください。
●医療証再交付の申請
【申請に必要なもの】
・医療証再交付申請書(ダウンロード)・父母等の養育者以外が申請される場合は、身分証明書の写し
・破損・汚損の場合は、お持ちのこども医療証 -
・ 対象者 ・ 所得制限 ・ 申請時に必要なもの ・ 注意事項 ・ 府外の医療機関にかかるとき ...(2023年8月1日 子育て支援課)
・ 対象者
・ 所得制限
・ 申請時に必要なもの
・ 注意事項
・ 府外の医療機関にかかるとき
・ 入院時の食事療養費について
・ 高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
・ 父子家庭等への医療費助成について対象者
柏原市に住んでおられる方で、次の条件を満たす方が受給できます。
・ 父母が婚姻を解消した児童
(児童とは18歳未満と18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者。以下同じ)
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が別途定める程度の障害状態(身体障害者手帳1・2級程度)
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで出産した児童
・ 前号に掲げる児童を監護(監督保護の意)し、生計を維持する父又は母、あるいは養育者
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方に所得制限があります。また同居される家族(祖父母や兄弟姉妹など)が居る場合には、その方の所得にも制限があります。
※所得制限の限度額についてはお問い合わせください。申請時に必要なもの
・ 健康保険証
・ 戸籍謄本及び遺族年金証書(遺族年金受給者の方。児童扶養手当受給者は不要)
※その他、申請者の状況により必要書類が異なります。注意事項
1日あたり1人1医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です(同一月内2回まで。3回目以降は無料)。
同じ日に総合病院などで多数の診療科で受診された場合は、500円までの自己負担となります(1つの病院として考える。ただし歯科除く)。
同一医療機関で診療を受けられた場合、入院と外来とは区別し、別途自己負担が必要です。
処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)は、薬局でのご負担はありません。
1ヵ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた差額については、払い戻しの申請ができます。
家族療養附加金や高額療養費が支給される場合は、それらの額を差引きして助成致します。保険者(保険証の発行元)から発行される支給決定通知書等をご持参ください。
ひとり親家庭医療助成を受けられた場合、こども医療助成は受けられませんので、こども医療証をお持ちの方は返還をお願いいたします。※訪問看護利用料の自己負担の一部についても助成します。(助成内容は上記と同じ。)
府外の医療機関にかかるとき
「ひとり親家庭医療証」は大阪府でのみ、ご使用出来ます。他府県の医療機関にかかるときは、医療費を一旦支払い、後日、市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)入院時の食事療養費について
入院した際の食事療養費は、大阪府内外を問わず、医療機関の窓口で一旦支払い、後日市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
ひとり親家庭医療費助成の申請をするまでに、先にご加入の健康保険へ高額療養費の申請してください。
領収書(コピー)に加えて、健康保険から発行されます支給決定通知書を添えてひとり親家庭医療費助成の申請をしてください。
また、治療用の装具・眼鏡の申請には、上記の【申請に必要なもの】の他、支給決定通知書、
医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)及び領収書のコピーの添付も必要です。※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをおとりください。
父子家庭等への医療費助成について
母子家庭だけでなく、父子家庭や両親が不在の児童を祖父母などが養育されている世帯に係る医療費について、その児童と養育者に医療費の助成を行うことができます。
所得制限があり、また戸籍謄本を提出していただくなど必要な書類がございます。詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。 -
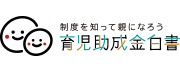 イクハクで子育て情報・相談窓口を調べる 育児助成金白書(イクハク)は、子育て世帯が受けられる制度と相談窓口を知る民間サイトです。 育児助成金白...(2021年11月15日 子育て支援課)
イクハクで子育て情報・相談窓口を調べる 育児助成金白書(イクハク)は、子育て世帯が受けられる制度と相談窓口を知る民間サイトです。 育児助成金白...(2021年11月15日 子育て支援課)イクハクで子育て情報・相談窓口を調べる
育児助成金白書(イクハク)は、子育て世帯が受けられる制度と相談窓口を知る民間サイトです。
育児助成金白書(イクハク)と大阪府は、子育て支援制度のきめ細やかな情報発信を目的に事業連携協定を締結しております。
イクハクでは、柏原市を含む全国1800以上の市町村別に30万を超える子育て制度と相談窓口を掲載しています。
サイトURL【外部サイトへ移動します】
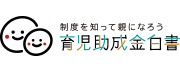
育児助成金白書(イクハク) http://www.ikuhaku.com/
柏原市が紹介されているページ http://www.ikuhaku.com/mains/systemlist/osaka/kashiwara_shi/
運営法人 一般社団法人日本子育て制度機構
所在地 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3-3-8 Rゲストハウス3階
連絡先 info@ikuhaku.com -
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害年金を受給しているひと...(2021年1月12日 子育て支援課)
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
厚生労働省チラシ
•児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます (PDF:598KB)
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
見直しの内容
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
上記以外の人
こども政策課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請に必要なものはこども政策課までお問い合わせください。申請期限
令和3年6月30日(水)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
-
1 制度全般について 1-1手続きは必要ですか。 1-2無償化の対象となる費用は何ですか。 1-3どのようにして支給されますか。 更新 1-...(2019年10月30日 こども施設課)
1 制度全般について
1-1手続きは必要ですか。
1-2無償化の対象となる費用は何ですか。
1-3どのようにして支給されますか。 更新
1-43歳から5歳までの無償化の開始年齢は、3歳になった日からですか。3歳になった最初の4月からですか。
1-5認可外保育所に通っています。無償化の対象ですか。2 申請書の書き方について
2-1認定希望日(施設利用開始日)はいつを記入すればよいですか。 更新
2-2マイナンバー(個人番号)は誰のものを添付すればよいですか。1-1 手続きは必要ですか。
ご利用状況によって異なります。こちら(無償化対象診断)からお調べください。
また、必要な場合、申請があった時点から無償化制度の対象となり、遡っての申請は受理できません。1-2 無償化の対象となる費用は何ですか。
保育料及び入園料となります。
延長保育料、時間外保育料のほか、主食費、副食費(おかず・おやつ等)、通園送迎費、行事費、保育用品費等の実費徴収費用は対象外となります。※副食費の取扱いに関してはこちら。1-3 どのようにして支給されますか。
まず、認定申請手続きが必要です。認定を受けられた方は、施設の利用後、給付のための請求手続きが必要となります。
ただし、ご利用の施設によって異なりますので、以下からご確認ください。
・認定申請手続きについてはコチラ
・給付のための請求手続きについてコチラ1-4 3歳から5歳までの無償化の開始年齢は、3歳になった日からですか。3歳になった最初の4月からですか。
3歳になった最初の4月からです。
ただし、幼稚園の満3歳児クラス入園の方は3歳になった日から対象となります。(預かり保育は対象外です。)1-5 認可外保育所に通っています。無償化の対象ですか。
こちら(無償化対象診断)からお調べください。
2-1 認定希望日(施設利用開始日)はいつを記入すればよいですか。
施設の利用開始日を記入してください。ただし、申請書の提出が施設の利用開始日より遅くなる場合は、提出する日付と一致させてください。
2-2 マイナンバー(個人番号)は誰のものを添付すればよいですか。
各申請用紙の保護者欄に記載された方の分のみ添付してください。
-
1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について 判定基準の調整を次の計算式で行います。 区分C:市民税...(2014年3月31日 教育総務課)
1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について
判定基準の調整を次の計算式で行います。
区分C:市民税所得割課税額が34,500円に①,②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。区分D:市民税所得割課税額が171,600円に③,④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。例として、扶養親族が
幼稚園児(5歳)(H19.5.2生まれ) 1人
小学生6年(11歳)(H13.5.8生まれ) 1人
高校3年生(17歳)(H7.12.20生まれ) 1人
の場合、16歳未満の扶養親族2人、16歳以上19歳未満の扶養親族1人なので、各区分の基準は下記のとおりになります。
区分C 34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
区分D 171,600円+(2人×198,000円)+(1人×7,200円)=218,400円
(年齢は平成24年12月31日時点で計算することに注意してください。)
市民税の所得割額を以上の基準額と見比べて区分を判断してください。
なお、扶養親族の人数と基準額をよりわかりやすく見ていただけるよう早見表を用意しております。
平成25年度版補助基準額早見表(PDF)市民税について
市民税は、住民税のうち、市町村に支払うものです。
平成25年度の市民税は平成25年1月1日時点で居住していた市町村において課税されます。平成25年1月2日以降に柏原市に転入されてきた場合は、平成25年1月1日時点でお住まいだった市町村で「課税(非課税)証明書」を取得していただき、申請書に添付して提出してください。区分 補助の基準
(平成25年度の市民税額)多子別区分 (ア)1人就園または
同時在園の補助金額
(1人年額)(イ)小学校1・2・3年生の
兄・姉がいる補助金額
(1人年額)A 生活保護を受けている世帯 第1子 229,200円 ― 第2子 268,000円 249,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 B 市民税が非課税の世帯
及び
市民税所得割課税額が非課税の世帯
(均等割額のみ課税)第1子 199,200円 ― 第2子 253,000円 226,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 C 市民税所得割課税額が
34,500円に①,②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。第1子 115,200円 ― 第2子 211,000円 163,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 D 市民税所得割課税額が
171,600円に③,④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。第1子 62,200円 ― 第2子 185,000円 114,000円 第3子以降 308,000円 308,000円 E 上記区分以外の世帯 第3子以降 308,000円 ― 2.補助金額の判定方法について
例:幼稚園児(4歳) 1人
幼稚園児(5歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:0円市民税の所得割が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(ア)一人在園または同時在園の区分になります。
適用される補助金額は
第1子「199,200円」(5歳児の幼稚園児)と、
第2子「253,000円」(4歳児の幼稚園児)になります。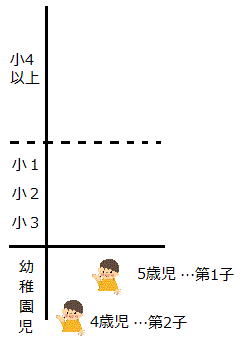
例:小学2年生 1人
幼稚園児(4歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:0円
所得割額:0円市民税が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、小学生2年生のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「226,000円」になります。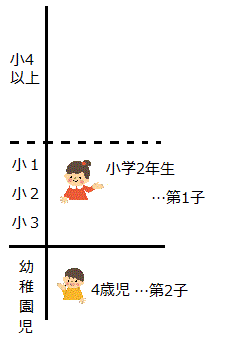
例:高校3年生(18歳) 1人
小学3年生 1人
幼稚園児(5歳) 1人<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:212,000円市民税課税基準額の計算式区分Cと区分Dを参照します。
16歳未満の扶養親族の人数が2人、
16歳以上19歳未満の扶養親族の人数が1人なので
区分Cの基準は34,500円+(2×21,300円)+(1×11,100円)=88,200円
区分Dの基準は171,600円+(2×19,800)+(1×7,200円)=218,400円
(早見表においては、16歳未満2人、16歳以上19歳未満1人の欄を参照)
となり、区分Dに該当します。
そして、小学生3年生のお子様一人と
年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「114,000円」になります。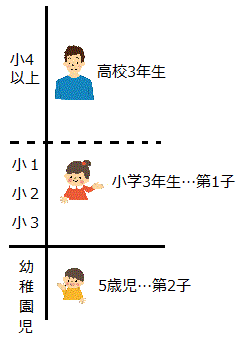
分野概要
-
児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 子どもの医療費助成 ひとり親家庭医療費助成 未熟児養育医療給付(2023年10月19日 秘書広報課)